2017年01月28日
10℃への挑戦
こんにちは!
昼間のビールの時間です。
今日は休日の予定でしたが、先輩の代わりに夜勤を引き受けたため、午後は昼寝する予定です。
夜勤の日には早朝フィッシングが恒例ですが、今日は強風予報のため断念しました。
散髪して・・・タックル整理をして・・・只今ビールを持ってPCの前に座りました。
先週までは極寒の海に漕ぎ出すのが億劫にも感じつつありましたが、前回の“爆”の余韻に浮かれ気分で、明日の夜勤明けの凪予報に心が躍らせれているところです。
ちなみに“爆”ですが、個人的に何となく10匹を目安に“爆”認定しています。
小物の数釣りでは10匹と言うのは物足りないですが、地元KFでは満足な型が揃い易いため、10匹も釣ると非常に満足感を得ることが出来ます。
その基準で言えば、昨年の“爆”認定は7回かな・・・?
余談でした。
さて今回は、イメトレ含めた一人作戦会議です。
まずはアイナメのシーズナルパターンに関して考えてみたいと思います。
※僕はプロアングラーでも生物学者でもないですから、個人的な限られた知識の中で考えています。
全てが正解ではないです。想像で書いています。ご了承を!
地元KFでは、ほぼオールシーズン釣ることが出来るアイナメですが、行動パターンを詳細に把握することが出来れば、狙うべきポイントや使うべきルアーが判断し易くなると思います。
まず、1/4(水)に後輩TZK船長の操船でボートスロジギをした時の話です。
海域としてはEP.NよりもEP.Oに近いエリアでした。
船中で数匹のアイナメが釣れましたが、沖の水深30~40mではメスが釣れて、湾内の水深20~30mではオスが釣れました。
この時期は産卵前後でオスが黄色い婚姻色となるため、区別が容易です。
沖でも美しいゴールデンのオスが釣れましたが、メスとは違うエリアで釣れました。
このことから判断したのは
①オス:産卵後で卵の見張り番をしているため、浅いエリアに多かった。
②メス:産卵後で体力回復のために浅場を離れて、深いエリアに多かった。
つまり“産卵後”と予想しました。
その旨の内容を船上でも発言していたのですが・・・
帰宅して腹を裂くと、立派な卵と白子が出て来ました。
オス・メスで釣れたエリアが分かれていたのは、たまたま偶然だったようです。
たった数匹のデータですから“たまたま”は起こりますね。
そもそも、卵の見張り番をしているオスは、それほど積極的には捕食行動をしないようです。
次に前回のNでのアイナメですが、ほぼ同じエリア内で8匹のアイナメを釣って、キープした4匹はオス・メスが半々でした。
釣った時の印象は、オスの婚姻色は盛期に比べて抜けつつありました。
腹を裂いたら、産卵後であることを裏付けるように、卵巣と精巣が萎んだ状態でした。
恐らく、産卵直後はメスが先行して回復のための捕食活動を再開し、続いて卵が孵化してからオスも捕食活動に合流した頃・・・かな、と考えました。
冬の間は、もう少し深いエリアにも落ちるのかとも思いますが、急傾斜ポイントの落ち込んだ“谷”である23m地点での釣果が多かったことから、この谷に居着いて時々は急傾斜の“山”である14m地点に甲殻類を探しに出るのかも?とイメージしました。
これから海水温が更に下がると、アイナメの活動は鈍くなるのでしょうか?
そうすると、小魚よりも甲殻類や虫エサを主食とするように思えるのですが。
そこから季節が過ぎて、5,6月になると40gほどの小型ジグに反応が良かった印象があります。
春になると浅い藻場で、タナゴ・メバル等の稚魚を主食とするタイミングがあるようですが、それを考えると、小さいシルエットに反応が良くなり更には積極的に水面まで追い食いして来たのも、納得です。
ここまでの考え方が、どこまで合っているのか謎ですが・・・
そもそも、釣りは“仮説を立てて実証することの繰り返し”が大事なのです。
石垣島の某S氏のブログで学んだ“開拓の秘訣”です。
特に地元海域でのKFは、全くの未開拓の段階から、ここまで開拓の過程を進んで来ました。
考えられる可能性や想定される事柄が無限にある状態から、やみくもに全てを試そうとする開拓方法では、追いつかなかったのです。
だから仮説を立てることを習慣としました。
その仮説は全くもって間違っている場合もあるのですが、それでも僅かでも可能性を感じるメソッドだけに絞って試せば、攻略への近道になることは確かだと思っています。
その“仮説を立てる”話としては、ここからが更なる本題です。
“海水温10℃”を境に、地元KFのシーズン“オン・オフ”と位置付けています。
それで、10℃を下回る2,3月には湾奥へ遠征するのが恒例なわけです。
が、、、10℃を下回っても何か可能性はないのか?
と、言う課題も、常々探り続けています。
例えば釣り船であれば、近い海域の遊漁船HPで釣果情報を確認すれば、2,3月でも釣果はあります。
でも、それは水深30~60mでのことです。
カヤックからのターゲットを判断するには、水深~20mでの釣果情報が欲しい。
そこで参考になるのはオカッパリ釣果情報と、小名浜沖堤(=水深20mほど)での釣果情報です。
例年2,3月の、これらシャローでの釣果情報だと・・・
①オカッパリから乗っ込みクロダイが釣れる!しかも良型!
②オカッパリ&沖提でカレイが釣れる!しかも良型!
③稀に沖提でマダラも!※これは遊漁船では冬のメインターゲット
上記3魚種は、この冬に試す価値はあるな、とは前々から考えていました。
クロダイは、水深~10mのシャローで、、、バイブレーション?もしくは、テンヤでも可能性はあるのだろうか・・・?
カレイは、虫エサを使用しての小突き釣り的なの・・・?
マダラは(KF的)ディープエリア(=水深20~30m)まで沖に出ることが出来る海況に限られるけど、お馴染みのスロジギをやれば、他の根魚の調査も含めて、イメージできる。
ここまでが、この冬を迎える前段階でのイメージでした。
それが昨日たまたま書店で珍しくジギング誌を購入したのですが、そこから更に有力な情報を得ることが出来ました。
例えば・・・
①春だと思っていたマダイの乗っ込みは、仙台湾では夏~秋と言われていること。
これは、カヤックからのマダイ釣果が数回あった時期と照らし合わせると、ここ福島県でも似たような時期なのかも。
②茨城県南部~千葉県では、1~4月にホウボウジギングなる釣りが流行っているらしい。
これは、その時期にホウボウが産卵のために接岸するところを狙ったものらしい。
ポイントの条件としては、水深20~80mで岩礁帯が絡んだ砂地・・・
これは、ポイントOから出艇した場合の西側で水深20~25mのエリアが当てはまるのでは??
昨7月にホエール氏が座布団ヒラメをキャッチしたエリアを含めて、そこから西側のエリアです。
そもそも地元海域でも、動力船では同様の時期にホウボウ“爆”が発生する時期でもあります。
だから、産卵のための接岸は、地元海域でも同様だと思います。
これらに加えて、前回のEP.Nでの“爆”も含めて考えると、海水温が10℃を下回っても、水深20mまで漕ぎ出ることが出来れば、可能性はあるのでは?と考えを改めるようになりました。
冬の間は海水温低下の他に、頻繁に底荒れが発生する悪条件も重なります。
これまでは、冬の間も時々は出艇していましたが、釣れない理由を“海水温”だけに決めつけてしまっていました。
そう考えている限りは“海水温が10℃に回復するまでは釣れない”との結論から抜け出すことが出来ません。
だけど、釣れない理由には“底荒れ”もあったのかも。
で、あれば底荒れが落ち着くだけの何日間か凪が続いたタイミングであれば、冬の地元KFでの釣果も可能性があるのかもしれない。
今のところは、冬の開拓ターゲットとしてクロダイ・カレイは2番手として、まずはスロジギで根魚,ホウボウ,マダラを探してみたいと思います。
それでは、夜勤に備えて昼寝します。
明日は釣果情報を投稿できるよう頑張ります!
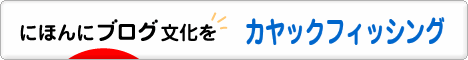
にほんブログ村
Posted by いわき2011 at 12:19│Comments(0)
│艤装&釣り談義
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

















